季節外れの暖かい日が続く中,2月に入り一気に寒くなってきましたが,普段のリズムも戻ってきて落ち着いてきたかなといったところでしょうか。1月はいく,2月は逃げる,3月は去ると言われるように,新年が明けましたが時間が過ぎるのは早く,もう1月が終わってしまいました。勤務先では期末試験が早く,もう既に1ヶ月を切っているので生徒もそうですが此方も試験準備をしなくてはと思うばかりです。
さて,前回は昨年より取り組んでいるTANABU Modelについて,4つのコースのうちの1である「こってりコース」のワークシートを紹介しました。
今回の投稿では,実際にこってりコースを運用する中で直面した問題や課題について紹介しようと思います。
前回の投稿は此方から。
TANABU Modelについては此方の書籍でご確認ください。
実施クラス
実施するコースとしては,各クラス30名前後の生徒ということもあり目も届きやすく,ペアワークやグループワークなどの活動を展開しやすいです。ただ英語力の幅は広く,クラスの中に英検2級を既に取得している生徒もいれば,日々の授業に苦労する生徒もいます。ただ,苦手な中でも前向きに取り組む生徒や人懐っこい生徒も多いので,活動には基本的に取り組んでくれます。
扱う教科書は高校1年生から継続して使用しています。教科書のレベルとしては平易なものなので,授業者としては工夫がしやすく,英語力に幅のあるクラスでも満遍なく指導できます。また,こってりコースではretelling活動があるので,もう少し頑張ればできそうという適度な負担で生徒たちも取り組むことができます。
運用する中での問題点・課題
当初はこってりコースの手順通り授業を実施していましたが,実際のクラスで運用する上では何点か問題点が出てきました。
| 時限 | ワークシート |
|---|---|
| 1時限目 | Paragraph Chart, Summary Writing, Reading Comprehension |
| 2時限目 | Vocabulary and Expressions Practice, Reading-aloud Activities |
| 3時限目 | Dictation, Retelling |
生徒でのやり取りの不足
まず,これはTANABU Modelというワークシートが進行の中心である特性故ですが,あまり生徒が英語でやり取りを行う機会が少ないという点です。TANABU Modelは便利なワークシートが用意され,これらを使用することで担当する授業者が複数であったとしてもある程度統一的に授業を行うことができる点は良い点かと思いますが,その一方でワークシートを配って取り組ませるという作業的になってしまう側面があります。もちろんこれはTANABU Modelに限った話ではありません。日々教科書会社さんも出版社さんも工夫を凝らして様々な教材を作成していただいている中で,教科書記載のアクティビティや指導書のワークシートは興味深いものも多いです。しかし,配布して取り組ませる「だけ」の授業はあまりにも無機質かと思います。私も初任時代はワークシートに教科書本文や空所を盛り込み,それを進める授業をしていますが,生徒がそこに書き込ませるだけの授業であったことを猛省しています。
ワークシートによってある程度画一的に実施できる一方で,教師も含めて教室に様々な背景を持つ人がいる教室の中で英語という教科である以上,やりとりによって予測不能なことが起こることも授業の面白い点かと思います。もちろんこってりコースの中では音読やretellingは用意されていますが,これはあくまで最終的な自由な活動に取り組ませるための練習活動であり,自由なやり取りにはなりません。新しい単元の導入や前のパートの復習の際にsmall talk (teacher talk)によって制限があるまでも生徒とのやり取りを行うことができればと思います。
要約活動での個人差
次に,1時限目の要約活動です。1時限目では英文の概要理解としてparagraph chartの後にsummary writingとして日本語で100字要約する活動があります。しかし,生徒の要約する力にはかなりばらつきがあり,すぐ終わってしまう生徒もいる一方で,要約が不慣れで(私もそうですが)時間がかかってしまう生徒もいます。そのため,reading comprehensionまでその時間で終えることができず,次の時間まで伸びてしまうことが多々あり,その分全体の授業時数が増えてしまい,授業計画の調整に難儀しました。
アウトプットまでの準備時間の確保
最後に,3時限目のアウトプット活動の準備時間です。2時限目のvocabulary and expression practiceとreading-aloud activitiesで生徒はそのパートの語彙や表現の確認と定着の活動に取り組みますが,その次の3時限目のDictationとRetellingでは,生徒の英語力に広がりがあるため,定着活動に取り組んだその次の授業ですぐにそれをアウトプットする活動に全員がある程度できるようには無理がありました。場合によっては前日の午後の授業に2時限目があり,翌日の朝に3時限目がある場合もあったので日々忙しい生徒には難しいことはもちろんのこと,家庭学習で取り組むことができるように授業の中で生徒がある程度身につけることができるようにすることも授業者の責務かと思います。
まとめ
今回はTANABU Modelのこってりコースを実際に教室で運用する中で見つけた問題点や課題について紹介しました。様々な背景や英語力を持った生徒がいる教室である以上,どんなアプローチもメソッドもそれだけでは上手くはいきません。それを使う指導者が教室環境に応じて調整することでどれだけ生徒の成長に寄与することができるかが重要であり,授業者の腕の見せどころです。
次回はその問題点や課題を踏まえて改訂したこってりコースについて紹介しようと思います。
皆さんの実践や研究の少しでも役に立てば幸いです。Tomorrow is another day.
参考文献
金谷憲・堤孝 (2017).『レッスンごとに教科書の扱いを変えるTANABU Modelとは―アウトプットの時間を生み出す高校英語授業』アルク出版.
Last Updated on 2025年2月12日
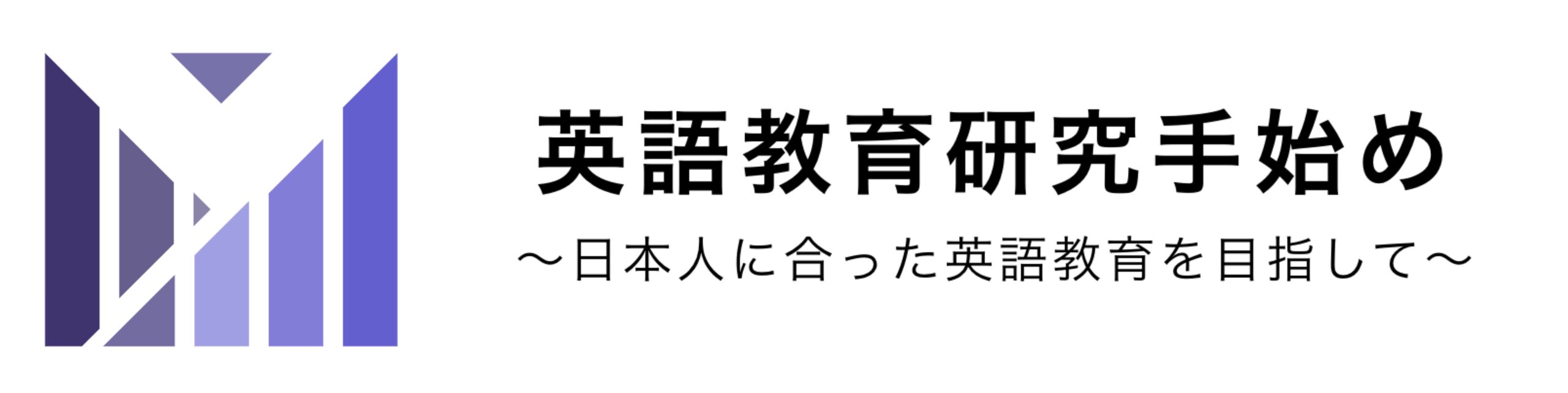




コメント