もう7月が終わろうとしていますね。6月下旬は学会発表もあり,そこから帰ると7月の期末試験や成績処理,そこから論文提出などもあり,あまりブログは更新できませんでしたが,8月以降はもう少し更新できればと思います。暑さが厳しい日が続きますが,皆様も体調面にくれぐれもお大事に,夏休みをお過ごしくださいませ。
さて,今回は少し前に紹介した大学受験指導の続きとして,英文和訳の指導がようやく固まってきましたので,その紹介をしたいと思います。
前回については此方から。
大学受験に向けての指導方針③〜英文和訳編〜
大学受験に向けて英文読解も重要ですが,その中の問題として内容理解以外に英文和訳もよく出題されるのではないかと思います。読解問題ではある程度概要で解答できる問題もあるかもしれませんが,英文和訳については精密な英文構造の把握と,その内容を正確に訳す技術が求められ,「こんな感じ?」のような訳では不十分であり,英文法の知識だけでなく,書き言葉の訳として判断することができる日本語力も必要です。そのための指導として実践を紹介できればと思います。
使用教材
英文和訳の教材としてはいいずな書店のSmart Readerシリーズと,数研出版のClues to Readingを使用しています。どちらの教材もトレーニングとしては最適なものであり,Smart Readerについては英COMの単位数の多い文系コースで,Clues to Readingは英語が得意な生徒も多い理系のコースで使用しています。Smart Readerについてはシリーズの中でstandardを利用していますが,レッスン数も豊富に用意され,その課の内容を練習するための問題が難易度順に用意され,また確認テストとしてそのレッスンの内容に関連した問題も収録されているので,クラスの中で難易度にばらつきがあっても,得意な生徒はどんどん解き,全体としてはこの問題までというように授業の調整がしやすいです。Clues to Readingについては本当に難解な英文ばかりが掲載されていますが,結局のところそのような英文を読み解くための基礎基本の要点が書かれており,どんなに複雑な文も基礎基本が重要であることを確認することができます。
運用方法
授業での運用としては,まず,基本的にはその教材を繰り返し使用できるように冊子自体は使わず,その教材からの英文を1つ載せ,下に「下書き」と「本番」として該当箇所の日本語訳を書かせるスペースを設定したプリントを作りました。下書きには,とりあえずの逐語訳やメモを書かせ,その内容をもとに本番のスペースにより日本語らしい訳を書くように指示しました。そして,その内容をGoogleフォームに提出するように指示しました。最初の何回かの授業では授業内にそのプリントを配布し,授業内で日本語訳を書かせていましたが,難解な文構造や普段あまり見ない単語に出会い,個人によってかかる時間はそれぞれであったため,普段あまり事前の授業準備より復習に取り組むように指示していましたが,こればかりは授業の時間を最大限に活用するために,前の授業の宿題として事前に提出するように指示しました。
授業当日は,前日までに生徒がGoogleフォームに提出した訳に目を通し,指摘しておいた方がいいところや,日本語にうまく訳することができているところを確認し,それらを伝えるために全体の訳の中から何個かの訳を選び,それらの一覧を生徒に配布するために紙に印刷しておきます。
授業ではまず生徒が書いてきた日本語訳をもとに,ペアで訳した内容を共有させ,該当箇所までの部分の訳を済ませます。その後,該当箇所について生徒の日本語訳の中で選んだものが記載されたプリントを配布し,その中で該当の英文の日本語訳として最も適切なものを考えさせます。そして,ついに該当箇所の説明に移りますが,ここでは全てを説明せず,まずは英文の構造のみを説明し,その後ペアでその説明をもとにどの日本語訳が適切かを再度話し合わせます。
そして,生徒にどの日本語訳が1番いいかを聞き,今回の英文の訳のポイントを説明します。これまで授業で主語と動詞をはっきりさせるように指導してきたつもりでしたが,やはりまだまだできていない生徒もいました。英文が長く構造も意味も複雑であるが故,読んでいるうちに整理しているうちに,よく分からなくなり曖昧な役になってしまうのでしょう。他には,最近の授業ではbindをどのように訳すかについて,辞書では「縛る」と書かれていますが,bind the earth to the sunと英文にあり,「地球を太陽に縛る」よりは「地球を太陽にとどめていく」などのような訳の方がより自然であるという話をしました。
その説明後は,改めて配布した日本語訳の一覧を確認し,それぞれどこを直した方が良かったかを説明します。その際には日本語訳としては訳し残しはないものの,節や句の順番など,どこにあった方が書き言葉としてよりわかりやすいかなどを指摘するようにしています。普段話し言葉ばかり使う生徒たちなので,書き言葉ではどう書いた方がより明瞭に意味を伝えることができるかを考えるように話しています。一方で,生徒たちが素晴らしい言葉遣いをしている際にも生徒に共有するようにしています。少し前の授業では「享受」という言葉を使い,文脈上もその言葉が適切であり,言葉遣いが素敵であることを共有しました。
人のふり見て我がふり直せ
この実践では人の日本語訳を見て分析する機会を持つようにしていますが,あまり人の日本語訳を見ても,なかなかどこがどの方がいいかなどを考えにくいと思います。しかし,これが自分の答案を見直す際の練習であることを生徒に伝えています。試験では自分が書いた英文を見直す際には,それが正しいと思い込んでしまい,改善点を見出すことはなかなかできませんが,人のものであれば気楽に(?)指摘することができるのではないかと思います。その際の第3者的な視点を自分の答案の際にもできるようになるための練習であると伝えています。
まとめ
今回は大学受験に向けての指導として英文和訳の実践を紹介しました。普段扱っている英文自体もなかなか難解になってきていますが,英文和訳の教材の英文となると,なお一層英文の構造も複雑で意味も抽象的になり,問題を事前に解いておくだけでなく生徒にどういったことを伝えるべきなのかを含めて事前の準備は骨がかなり折れます。しかし,そもそもの出典が実際の書籍や新聞の記事などであることもあり,さまざまな表現や言い回しに出会うことができ,自分の英語の見直しになり,英文を読むこと自体はどんどん面白くなってきています(生徒にはいい迷惑でしょうけど笑)。この1月から本格的に大学受験に向けた英文を読むことが多くなり,論文を書く際や学会発表で話す際の英語が少し改善されてきているように感じます(それでもまだまだですが…)。7月末までの補習が終われば,授業も残り少しとなり,時間的にできることも少なくなってきますが,生徒1人1人の英語力を少しでも伸ばすことができるように尽力したいと思います。
皆さんの実践や研究の少しでも役に立てば幸いです。Tomorrow is another day.
Last Updated on 2025年7月27日
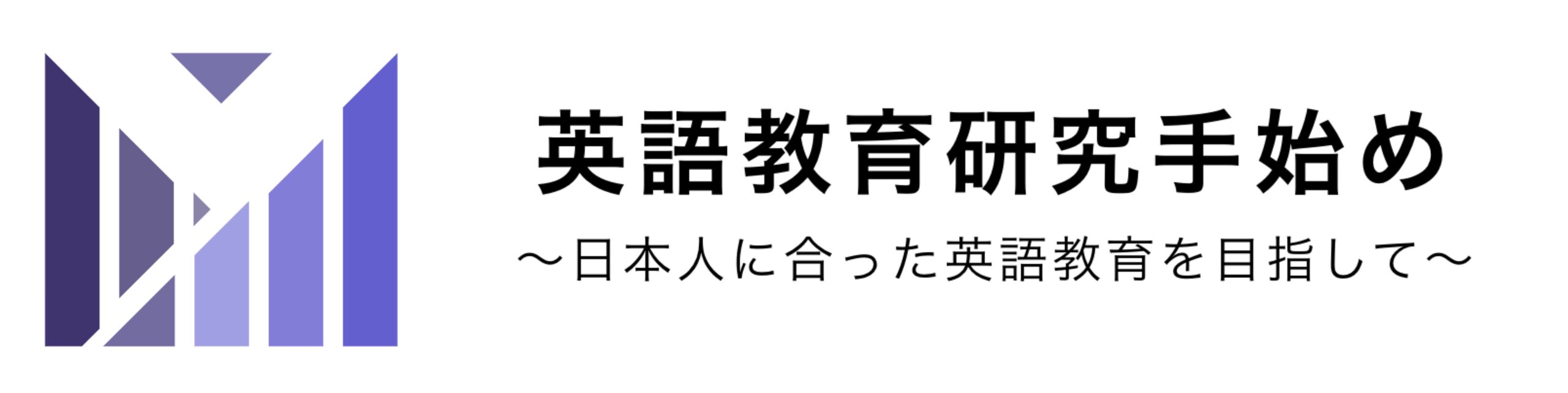




コメント