2025年度が始まり少し経ち,4月に入ったにもかかわらず寒い日が続きますが,やっと暖かくなってきましたね。学級開きや授業開き,その他の業務で色々とお忙しいとは思いますが,あまり気負うことなく,まずはGWまでほどほどにやっていきましょう。
今回の投稿からは,今年度の授業方針について書きたいと思います。初めて高校から特進系を担当して3年目,ついに大学受験の1年を迎えることになりました。実際のところ大学受験まで1年には満たないのですが,受け持つ生徒たちが全力を尽くすことができるように尽力していきたいと思います。その今年度の実践として,今回は語彙指導について紹介したいと思います。
大学受験に向けての指導方針①〜語彙編〜
大学受験英語の基礎基本といえばやはり語彙ではないかと思います。語彙の意味が分からなければ,書かれた文章の内容も聞こえてくる音源の内容も分かりません。特に,共通テストが導入されてからは,センター試験のように内容が分かれば正答することができるものではなく,内容が理解できた上で暗示された内容を考える必要があり,英文や音源を理解する上で語彙がますます重要になってきているのではないかと思います。もちろん無限にある単語を全て暗記することは不可能ですが,多くの語彙を身につけている方が有利であることは事実でしょう。身につけた語彙量が圧倒的に違うにもかかわらず,模擬試験の点数が同じくらいというのは考えにくいのではないかと思います。そのため,大学受験はもちろんのこと英語学習においても語彙は重要であり,これまでどのように運用してきたかも含めて,今年度の運用方法を紹介したいと思います。ただ,語彙学習自体はリーディングやリスニングなどの英語学習のどの部分も結果的には語彙学習になるので,今回は単語帳を使用しての語彙に集中した学習とします。
使用教材
語彙学習としての使用教材については,これまで1年次には数研出版さんのLEAP Basic,そして2年次からはLEAPを使用してきました。使用した経緯としては,あまり特進系の経験がなかったため,前年度の学年が使用していたものをそのまま踏襲する形となりました。LEAPについては昨年改訂されましたが,改訂前のものを引き続き使用しています。
運用方法(昨年度)
勤務先では毎週木曜日の朝礼で英単語のテストが実施されているので,1年次よりそのタイミングでの単語テストに向けて単語帳を使用しています。
出題方法としては,1つの単語帳の中で日本語から英語と英語から日本語で,それぞれ別の範囲を設定し,スペルを書かせることはせず,まずは単語と意味を繋げることを目標とし,どちらも4択問題で出題してきました。
大学受験に向けて語彙は広く(どれだけ知っているか)そして深く(どこまで知っているか)身につける必要があると思いますが,その中でもまず優先するべきは広さ,どれだけ知っているかだと考えます。そのため,まずはより多くの語彙とその意味をつなげることを目標にしました。
一方で,スペルを書かさなくてもいいのかという意見もあるかもしれません。もちろんスペルを書くことができることも重要ですが,中田(2019)では,単語の書き取り練習によって,語系と意味のマッピングなど,語彙の知識の他の側面の習得を阻害するかもしれないという研究が紹介されています。確かにスペルを書くことができることを語彙を身につける最終ゴールに置きがちですが,学習者にとっては,新たな語彙を学習するにあたって,単語・意味・スペルの3つとも身につける必要があり,それぞれのマッピングには負荷がかかることは当然かもしれません。そのため,大学受験に向けて膨大な語彙を身につけるために,まずは語彙と意味をより多くマッピングすることを方針としてきました。
また,出題形式について,語形と意味のマッピングにあたっては多肢選択問題と記述問題では同じくらいの効果があることが先ほどの中田(2019)で紹介されていたので,形式は多肢選択問題の4択問題としました。
もちろんスペルの練習をする必要がない以上,その分,範囲については少し広く設定し,単語帳自体を1年間で何度も繰り返すことができるようにしました。また,1度見ただけではなかなか定着まではいかないので,前回と次回の範囲が重複するようにし,繰り返し同じ単語に出会うことができるようにしました。
| 英語から日本語 | 日本語から英語 | |
|---|---|---|
| 第1回 | No.1-200 | No.371-430 |
| 第2回 | No.101-300 | No.401-430 |
| 第3回 | No.201-400 | No.431-490 |
| 第4回 | No.301-500 | No.461-520 |
| 第5回 | No.401-600 | No.491-550 |
運用方法(今年度)
その昨年度の運用を経て,同じ範囲を何度も繰り返してきたので,今年度からは今までの4択形式から,英語から日本語の範囲は英文の空所補充問題に,日本語から英語の範囲はスペルを書かせる問題に変更しました。
英語から日本語の範囲の空所補充問題は,英検の大問1で出題されるような問題です。これまでは英語を見て意味としての日本語を選ぶ形式でしたが,実際に英文を読む中で適切な語彙を選ぶことができるように難易度を上げました。
ただ,自力で毎回単語リストから選択肢を考えて,正答の語彙が入るような英文を何個も作ることは実用面から不可能です。しかし,生成系AIのおかげで簡単に作れるようになりました。ChatGPTのビルダー機能を使用し,範囲の語彙を入れればその語彙を基に英文の空所補充問題を10個作成してくれるChatGPTを作成しました。
もしご興味あれば使用してみてください。範囲の語彙を入れると事前に設定したプロンプトを基に問題を作成してくれます。
日本語から英語については,よくある形式ですが,単語帳に書かれているフレーズや文について,一緒に書かれている英文の意味である日本語を見ながら,その中の範囲の語彙のスペルを書く形式にしました。スペルが語彙と意味の結び付けを阻害するかもしれないという話を紹介しましたが,これまで繰り返し日本語から英語の意味のマッピングを繰り返し練習してきたので,スペルの練習をすることによっての阻害は少ないのではと考えました。また,日本語から英語の範囲については単語帳の序盤から半分ほどまでを目標とし,既にある程度身につけている語彙に絞り,それをより定着させるようにしました。特にそれらの語彙は大学受験でもライティングで使用するだろう語彙なので,ここで身につける練習をさせようと思いました。
まとめ
今回は今年度の大学受験に向けての指導の語彙面について紹介しました。スペルや選択肢式など色々なやり方があるかと思いますが,今年度はこの運用方法でまずは進めていきながら,修正の必要があればしていこうと思います。ただ,一方で単語帳が本当に必要なのかと思う部分もあり,その内容についてはまたどこかでまとめようと思います。
皆さんの実践や研究の少しでも役に立てば幸いです。Tomorrow is another day.
参考文献
中田達也 (2019).『英単語学習の科学』研究社.
Last Updated on 2025年4月18日
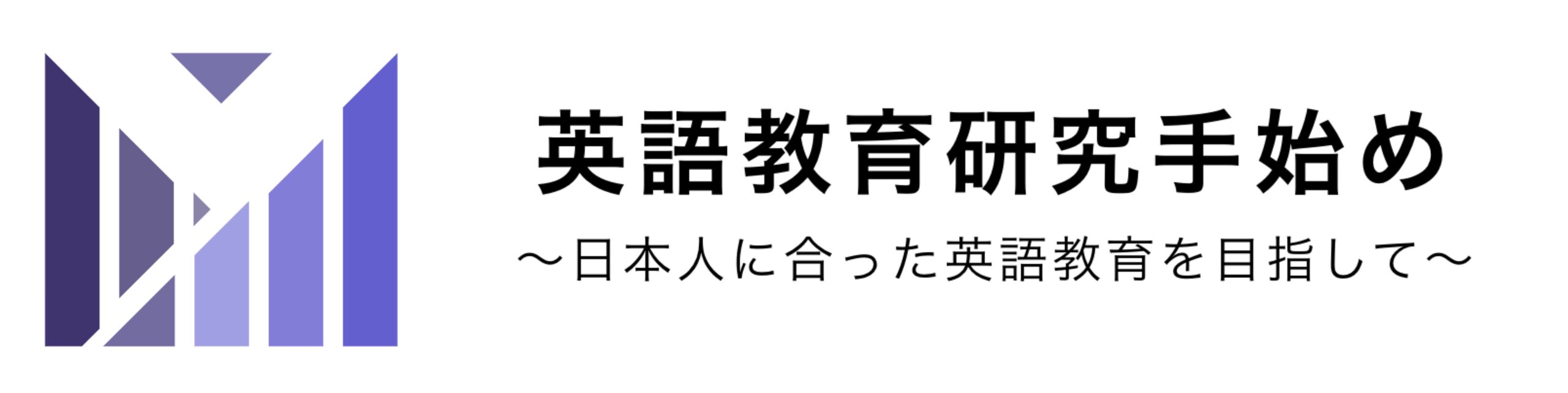



コメント