早いもので6月が終わり,2025年も半分が終わり,7月に入りました。暑さはますます厳しくなりますが,皆様いかがお過ごしでしょうか。私は先日,中部地区英語教育学会の山梨研究大会に参加して帰ってくると期末試験,そして成績処理を終えて,やっと落ち着いてきたところです。
今回の投稿では,その中部地区英語教育学会山梨研究大会に参加して考えたことについて,主に自由研究発表について紹介したいと思います。
中部地区英語教育学会HP
第54回中部地区英語教育学会山梨大会

第54回中部地区英語教育学会山梨研究大会に参加して
まず最初に参加したのは,富山大学教育学部附属中学校の中川拓也先生による「英語学習における自律的学習者の育成 −形成的評価としてのパフォーマンステストを通して−」でした。発表では,中学校1年生を対象に,自己紹介のスピーチ活動の実施に向けて,生徒と相談しながら評価規準を作り上げていくことで,生徒が自分の学びに責任を持ち,自律的学習者へと育てていく取り組みが紹介されました。生徒たちと相談しながら,あくまで教師が求める像を押し付けず,評価規準を作っていく様子が興味深かったです。
次は,奈良県立国際中学校・高等学校のHagihara Kosuke先生による“The impact of routine practice and formative assessment on impromptu speaking in junior high school”に参加しました。中学1年生を対象に,流暢性を高めることを目的とした,帯活動での即興型スピーキング活動が紹介されました。5回の帯活動の途中で1度だけ事前に記録した生徒の英語に対して授業内でフィードバックを行うことも相まって,帯活動全体を通して発話中の語彙数は増加していき,生徒たちの英語に対しての英語学習への好意的な気持ちが高まっていました。
続いての大阪府立水都国際中学校・高等学校の黒木浩亮先生と名城大学の藤原康弘先生による“Raising High School Students’ Awareness of English Diversity through a GELT Project”では,高校生を対象にGlobal Experiential Learning and Teaching(GELT)を基にした授業を実施し,世界の様々な英語についての理解を高めていったことが報告されました。そして,活動を通して自分の英語に自信がなかった生徒も自信を身につけていったことを聞いて,国際英語の重要な役割と思いました。
最後に参加したのは,山梨県立吉田高等学校の藤原剛「明示的知識の定着と動機づけの関係−自己決定理論に関する質的研究−」でした。高校生に対して文法の理解に焦点を当て,しっかりと身につけさせる指導と生徒の感想が紹介され,集計されたアンケートでは文法を中心に生徒の「わかるようになりたい」という気持ちが見られ,やはりまずはちゃんと理解できるようにしてやらねばと思いました。
今回参加して
今回,自分の発表もあることや藤原先生,萩原先生の発表を聞いて,活動を与えるばかりではなく,生徒が話すことや書くことをできるように保証することが英語教師としての責務であることを改めて感じました。所謂コミュニケーション活動が第二言語習得が示す通り(?)というような理由からか広がりを見せる一方で,生徒が「わかるようになりたい」・「できるようになりたい」という気持ちをどれだけ汲むことができているか甚だ疑問が残ります。それゆえ,まずはしっかり身につけさせてできるように繰り返して,言えることを増やしてからコミュニケーション活動へ繋げていくことが,習熟度の高い学習者のようなrare speciesではなく,beginnerやlower-intermediateがほとんどである日本の中高生の英語指導ではないかと改めて考えるばかりです。
また,中川先生の発表を聞いて,関西英語教育学会の今年の研究大会で畿央大学の福島先生のお話を聞いて以来,一般的に評価では点数が決められがちだが,生徒の個々の発達段階に応じて,次の段階はそれぞれであり,果たして評価する必要があるのかと考えるようになりました。本来形成的評価は点数や成績をつけるためのものではなく,生徒それぞれの成長のためにあるものであり,評価と成績は,混ぜて考えがちですが,しっかりと分けて考えたなくてはならないと思いました。
黒木先生と藤原先生の発表では,国際英語への意識が高まったと報告されましたが,自分の生徒たちでも同じようにいくかは少し疑問が残り,イギリス英語やアメリカ英語の違いでさえもわからない日本の中高生も多く,様々な英語があることを理解するためにはまずは英語運用能力をある程度身につけていく必要があるのではないかと思いました。GELT自体は興味深い指導法であるので,今月の英語教育8月号で詳しい内容を是非ご確認ください。
まとめ
今回の投稿では先日参加した中部地区英語教育学会山梨研究大会について紹介しました。
実は最初に参加した中部地区英語教育学会の研究大会も山梨でした。当時は大学院1年生で,その翌年に初めての学会発表に向けて学会の雰囲気を確認するために参加しましたが,単なる無名の学生であり,どこの部屋でも懇親会でも居場所がなく,指導教官の先生についていくだけでした。あれから10年経ち,大して成長はできていませんが,色んな人と知り合いになり,後輩たちとも一緒に参加することもでき,あの頃とは違うことを実感しました。
来年は奈良での開催です。自分も運営に関わるので,皆様のご参加をお待ちしております!
皆さんの実践や研究の少しでも役に立てば幸いです。Tomorrow is another day.
Last Updated on 2025年7月13日
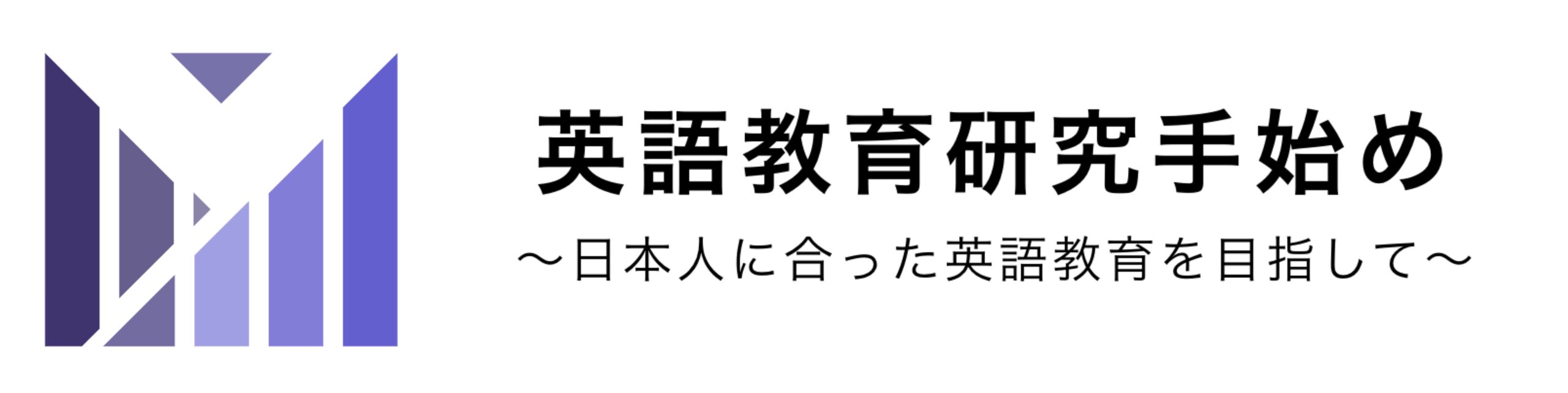



コメント