5月も後半になり,急に蒸し暑くなってきましたね。今年も昨年以上に暑くなるという予想もあるようで,先が思いやられますね… ただ,個人的には暑いよりは寒いほうが苦手なので,まだ暑さは何とかです。
さて,前々回から生成AIについて書き,前回は実際にChatGPTを使ってみての問題点について紹介しました。
今回は,生成AIの利便性や問題点を踏まえて,考えたことについて書きたいと思います。
今こそ英語教師が身につけるべき専門力
表題は大きな内容ですが,何も特別な内容はありません。ですが,こんな時代だからこそ尚更,英語教師は自分の英語力と専門性について向き合わなければならないと思います。
英語の専門力
まずは,やはり英語教師として,当然,自身の英語力が最重要でしょう。これまで紹介してきたように,ChaptGPTなどのAIは大変便利であり,我々英語教師にとって頼りになる相談相手や相棒になることでしょう。しかし,たとえAIでも,英語の誤りはあります(今のところは?)。AIが生成した英文を間違っているにもかかわらず,そのまま生徒に提示してしまっては,生徒に間違った内容を教えてしまいます。英語を教える英語の専門家として,AIが作り出した英語の間違いに気づく,もしくは,間違えていることまでは指摘できなくとも,有用性に盲目にならず,違和感を持つためにはその地盤となる専門力,英語教師であれば英語力が必要不可欠かと思います。
英語教育の専門力
また,英語だけでなく英語教育の専門家としては,AIが作成した英語の問題や評価規準について,妥当性や信頼性の面で判断できるように,我々自身の専門性を高めていく必要があります。前回紹介したように,作成した語彙問題についても他の選択肢でも答えになってしまうような信頼性の問題が起きることがあります。そんな時に問題の修正をできるように,英語教育のプロとして専門性を授業や評価などについても専門性を高める必要があるかと思います。
教師の役割
最後に,今の世の中の変化の中で教師の仕事がどうなるのかのような議論を見ることがありますが,教師の役割は本当に変わっていくのでしょうか。結局のところ,生成AIが台頭したとしても,それを巧みに使って授業する教師もいれば,それの言うままに授業をする教師がいるだけでしょう。しかし,これは今の時代だからこそというわけでは有りません。教科書や指導書のままに授業をする人もいれば,それをうまく使って授業をする教師がいるのと同じです。要は,教科書を授業するのではなく,教科書で授業するのと本質的には同じままです。
また,どんな教材であったとしても人が作ったものである以上,間違いや加筆修正する必要もあります。内容的に誤植等もあるかもしれませんし,編集の都合以上仕方ありませんが,教科書等が発刊するまでは多少の時間がかかり,この急激に変化していく時代の中で,記載内容が変更する必要も出てくるかもしれません。そのため,授業者として様々な分野の下調べは可能な限りでやっていく必要もあるでしょう。
そして,教師の役割として何より重要なのは,手本を示すことだと思います。生徒への生成AIの使い方の模範として,生成AIが出してきた内容に対して間違いがあることを見つけることや,疑問を感じ調べてみる姿を示すことで,情報をただ鵜呑みとせず自ら探究していくことに繋げていくことができるのではないかと思います。
使うことで効率が良くなる?
これは余談ですが,AIを使うことで仕事の効率を高めることができるとよく言われていますが,果たして本当にそうでしょうか。もちろん文書作成など本当に便利ですが,その内容のチェックや調整など,結局余計に時間がかかってしまっているようにも感じます。本当は自分がノウハウをちゃんと知っていれば,何事も自分でやることができれば本当は何より効率的ですからね。皆さんも色々とプロンプトを入力しているうちに,結局時間がかかってしまっていることありませんか?
まとめ
今回は生成AIを使ってみて,これからの英語教師に必要なことを考えました。
AIについては,もっと様々な利用方法をご存知の方もいらっしゃるかと思いますが(授業者もいらないぐらい?),自分が知らぬ間にコントロールされていないかと感じることがよくあります。
ChatGPT等の生成AIは決して完璧ではありません。それゆえ,AIが決めたことに対してただただ従うような状態ではなく,あくまで主導権は此方にあるとして,我々人間が主体性を固持しなければなりません。我々人間に主導権があるようにしていかなければなりません。
皆さんの実践や研究の少しでも役に立てば幸いです。Tomorrow is another day.
Last Updated on 2025年5月22日
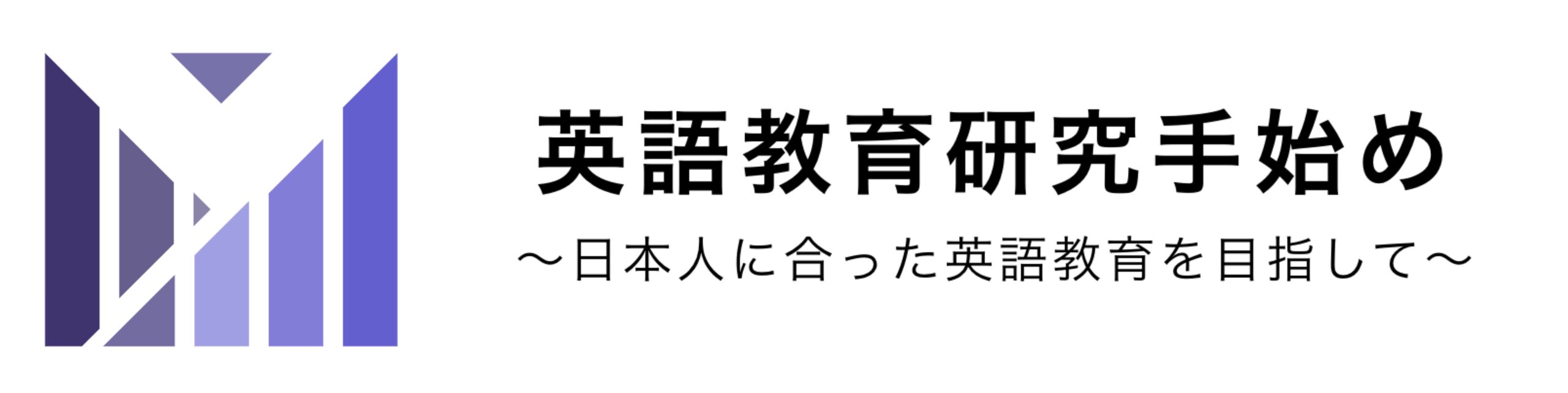




コメント