さて,そろそろ中間試験が近づいてきていますね。昨年度まではテストを毎定期試験で3種類作成する必要があり,毎回何とか期限以内に作成していましたが,今年度は2本となり,余裕がある分,テストでも生徒たちの英語力を高めることができるように準備を進めていきたいと思います。
今回の投稿からは,一昨年末より注目され続けている生成系AIについて,今年度も使っていく中で改めて考えたことを,実際の使用も交えながら書きたいと思います。
まず今回は,普段どのようにしているかを授業を中心に紹介したいと思います。
生成AIの使用例
昨今はAIも世の中に定着し,身の回りの様々なものにAIが組み込まれています。私も日々,何かを調べる際にはGoogleではなく,ChatGPTに尋ねることが多くなってきました。携帯にもアプリとして入っているので,そのものを調べるときではなく,言葉の使い方や違いなど複雑な調べかたをする際に使用しています。授業でのAIの使用としては,主に英文の空所補充問題の際に使用しています。
英文空所補充問題作成
英文の空所補充問題では,英検の第1問のような英文中の空所補充の問題を作成する際に使用しています。元々は毎週実施する英単語テストに関して,これまでは英文中のとある単語の意味を選ぶ問題や,日本語で書かれた意味から英語を選ぶ問題を出題していましたが,高校3年生になったので,英語を見て意味を判断する形式の少し難易度を上げるために,英文中の空所を埋めるような問題を手軽に作ることができないかと考えていました。以前にもChatGPTを使って,定期試験の問題作成の際に,そのような問題を作成していたのですが,作成された英文を精査するために,1つ1つの英単語に対して,毎回同じような指示をしていたので,どうにか自動化できないかと考えていました。そんな時に,ChatGPTのビルダー機能を見つけ,範囲の単語を入力すれば自動的に必要な問題数を作成するようにしました。
色々と操作しながら問題作成の自動化を調整していたのですが,最終的な指示としては次のようにしました。
- 「英検の第1問のような英文中の空所補充問題を作成する」
- 「解答のための選択肢は4つ」
- 「選択肢は入力した語彙からのみとする」
- 「選択肢は別の問題のものと被らないようにする」
- 「正答となる英語の品詞が偏らないようにする」のようなものを入力しました。
また,問題作成として,「解答の選択肢が偏らないようにする」,「解答一覧と解答を含めた英文の日本語訳を別に作る」というようなものも設定しました。
このおかげで,語彙問題について,単に英語を見て日本語を選ぶ,または書かせるような問題よりさらに難易度を上げた問題を作成することができ,身につけた単語の知識を実際に英文を読む中で使用する練習をすることができます。
授業での位置付けなど,此方の記事でも書いていますので,是非ご確認ください。
まとめ
今回は生成AIについて考えるシリーズの最初として,授業のどのようなところで生成AIを使用しているかについて紹介しました。生成AIのおかげで,これまでできなかったこと,もしくはできるまで時間がかかっていたことが簡単にもしくは短時間でできるようになりました。今後も授業をどんどん変えていくのは間違いないでしょう。
ただ,光もあれば影もあります。次回は生成AIの使用について気をつけるべきことについて紹介したいと思います。
皆さんの実践や研究の少しでも役に立てば幸いです。Tomorrow is another day.
Last Updated on 2025年5月14日
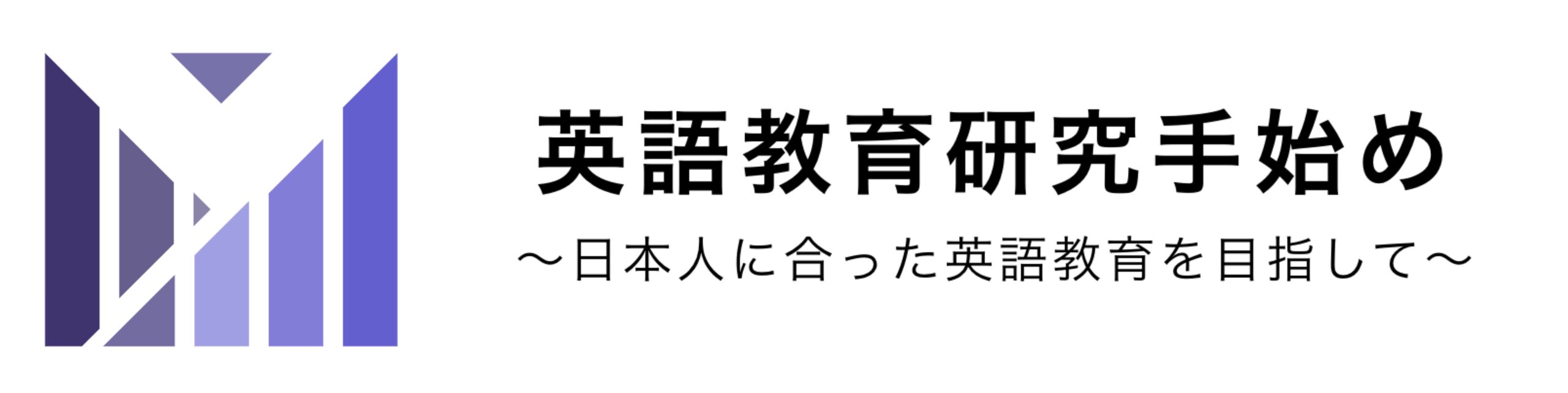




コメント