4月もあっという最終週を迎え,短かったような長かったような4月が終わりますね。初期行事等で落ちつかない日々の方も多かったと思いますが,新年度の最初の1ヶ月,皆様いかがでしたでしょうか。
さて,少し前にTANABU Modelの授業について紹介してきましたが,TANABU Modelは比較的,高等学校で行われている実践かと思います。それに対してというわけではないですが,教科書の繰り返しという点では中学校では5ラウンドという取り組みがあります。5ラウンドについては以前から書籍や学会発表等で知識としては知ってはいたのですが,実際の取り組みを見る機会があまりありませんでした。そんな中,近くで5ラウンドを取り組んでいる学校があるということを聞き,先日やっと学校を訪問し,5ラウンドの授業を見学することができましたので,今回からは5ラウンドについて書いていきたいと思います。
今回の投稿では,学校見学の内容の前に,まず5ラウンドとは何かについて紹介したいと思います。
5ラウンドについては此方の書籍をご確認ください。
5ラウンドとは?
5ラウンドは,横浜市南高等学校附属中学校で実施された指導法であり,その最大の特徴としては年間で1冊の教科書を5周します。その5周を通して,繰り返しインプットを与え,最終的にアウトプットのレベルまで持っていきます(金谷,2017)。
では,具体的にどのように教科書を繰り返すかというと,メインとなる10単元を1から10まで扱う1周を1年間で5回実施します(2,3年生は4ラウンド)。
| ラウンド1 | ラウンド2 | ラウンド3 | ラウンド4 | ラウンド5 |
| Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6 Lesson 7 Lesson 8 Lesson 9 Lesson 10 | Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6 Lesson 7 Lesson 8 Lesson 9 Lesson 10 | Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6 Lesson 7 Lesson 8 Lesson 9 Lesson 10 | Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6 Lesson 7 Lesson 8 Lesson 9 Lesson 10 | Lesson 1 Lesson 2 Lesson 3 Lesson 4 Lesson 5 Lesson 6 Lesson 7 Lesson 8 Lesson 9 Lesson 10 |
各ラウンドでの活動内容
それぞれのラウンドでは,音声の理解のインプットからアウトプットとしてのリテリングまでを徐々に実施します。
| ラウンド | 内容 |
|---|---|
| 1 | リスニングによる内容理解 |
| 2 | 内容理解した本文での音・文字の一致(1年生のみ) |
| 3 | 音読 |
| 4 | 穴あき音読 |
| 5 | リテリング |
ラウンド1:リスニングによる内容理解
まず最初のラウンドはリスニングによる内容理解です。目的としては,教科書内容の概要を音声面で理解することです。もちろんただ聞くだけではなく,聞いた後に生徒たちは教科書のピクチャーカードを音声で流れた内容順に並び替えます。生徒たちは正しい順番に並び替えることができるように,ゲーム感覚で何度も繰り返し集中して音声を聴くことができます。その後は,生徒とやりとりをしながら,正しい並び順の確認を行います。追加の内容理解として,教科書のQAに取り組ませることや登場人物になりきってのリスニングやスピーキングも行うことができます。
ラウンド2:内容理解した本文での音・文字の一致(1年生のみ)
次に,ラウンド2の音と文字の一致です。これは文字の入門期である英語初学者である中学1年生で実施します。ただ,生徒の習熟度に応じて2,3年生でも実施できると思います。内容としては,教科書の音声を聞いて,順不同に提示された教科書本文を聞こえた順に並び替えます。これもラウンド1の教科書本文のピクチャーカードの並び替えと同じように,生徒も集中して楽しく取り組むことができます。
ラウンド3:音読
ラウンド3では,いよいよ定着の段階として音読を始めます。もちろん1時間の間に同じような音読ばかりをしていては生徒たちは退屈に感じるので,一斉読みやペア読み,オーバーラッピング,シャドーイングなど,様々な音読方法を組み合わせて教科書表現の定着を図ります。そして,登場人物になりきる音読や,教科書を見ないで言ってみるなどによって,生徒たちにより刺激を与えることができるかもしれません。また,生徒の頑張りの評価として,音読テストをここで実施することもできるでしょう。
ラウンド4:穴あき音読
いよいよ終盤に近づき,ラウンド4では,穴あき音読として,これまで何度も聞いて読んできた英文の穴あきや並び替えのものを,自分で考えながら音読していきます。同じ英文ですが,ペアやグループを変えることでゲーム感覚で行うことができ,また穴の数を調整することで難易度の調整も行うことができ,先ほどのラウンドで紹介した,最終的に教科書を見ないで音読するレベルまで段階的に取り組ませることもできるでしょう。
ラウンド5:リテリング
最後のラウンドはリテリングです。これまで何度も繰り返し取り組んできた教科書内容をいよいよ自分の言葉でアウトプットするタイミングです。ピクチャーカードなどを使いながら,教科書の本文の丸暗記の部分もありながらも,それも含めて自分で表現を選んで,リテリングをします。このラウンドもペアやグループなどで相手を変えることで繰り返すのはもちろんのこと,教科書の表現のヒントの数を調整することで難易度も変えることができます。また,スピーキングでのリテリングの後には,話した内容を書くことでライティングの練習もすることができます。
ラウンド以外にも
ここまで5つのラウンドを紹介しましたが,もちろん5ラウンドでは紹介したラウンドだけを授業でしているわけではありません。毎回のラウンド前にはチャンツや動詞の確認などのウォームアップ活動が行われ,ラウンド前の授業の雰囲気作りや準備運動をしています。また,チャットのような生徒や教師と英語で話してみる活動にも取り組みます。そこでは,今まで学習した表現を自由に用います。
一方で,5ラウンドでは5つ目のラウンドであるリテリングがゴールと思われるかもしれませんが,リテリングもコミュニケーション活動としては練習に近いものであり,そこで終始するのではなく、その成果の確認として,意味に焦点を当てたコミュニケーション活動もゴールとして設定する必要があるということを学会での発表でも強調されていました。授業時数や生徒の人数など,色々な要因でなかなか5ラウンドだけでも時間を確保するのが難しいかもしれませんが,せっかくここまで教科書の表現を定着してきた以上は,最終ゴールとしてコミュニケーション活動まで実施したいですね。
まとめ
今回は5ラウンドの概要について紹介しました。教科書を繰り返し行うことでインプットの質を高め,アウトプットできるレベルまで底上げを目指していく活動によって,生徒は教科書の内容は分かるし,話すことも書くこともできるという気持ちを持つことができ,それが自信となり,前向きな気持ちを持つことができるのではないかと思います。
ただ,今回5ラウンドについて紹介しましたが,実際に自分では実施したことがなく,また今回は簡単な概要の説明程度にしているので,興味を持った方は是非書籍を手に取ってみてください。
次回からは実際に5ラウンドに取り組まれている学校での授業見学について紹介したいと思います。
皆さんの実践や研究の少しでも役に立てば幸いです。Tomorrow is another day.
参考文献
金谷憲 (2017).『英語運用力が伸びる5ラウンドシステムの英語授業』大修館書店.
Last Updated on 2025年5月2日
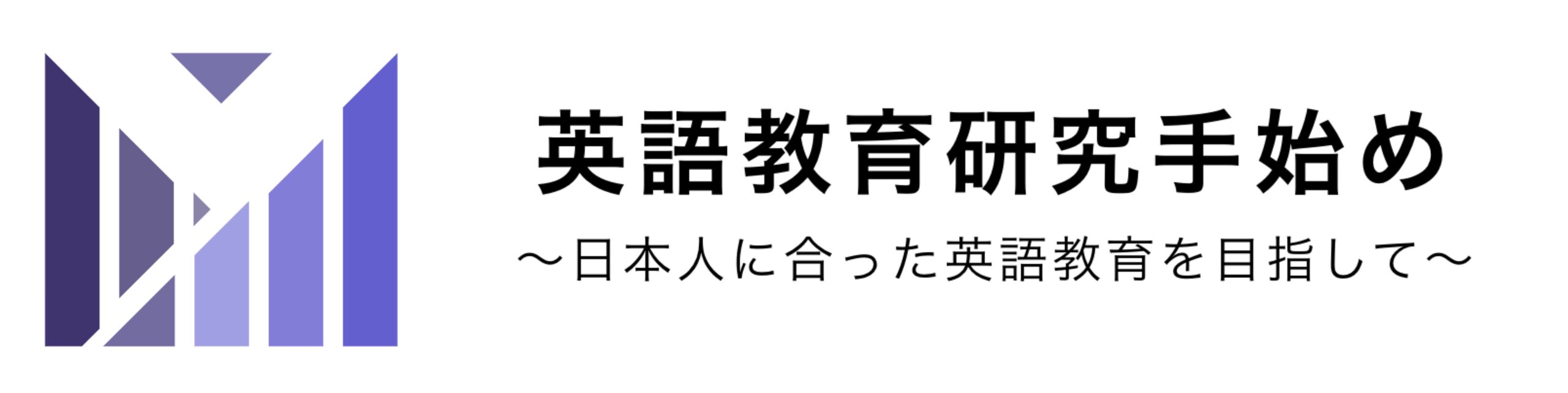
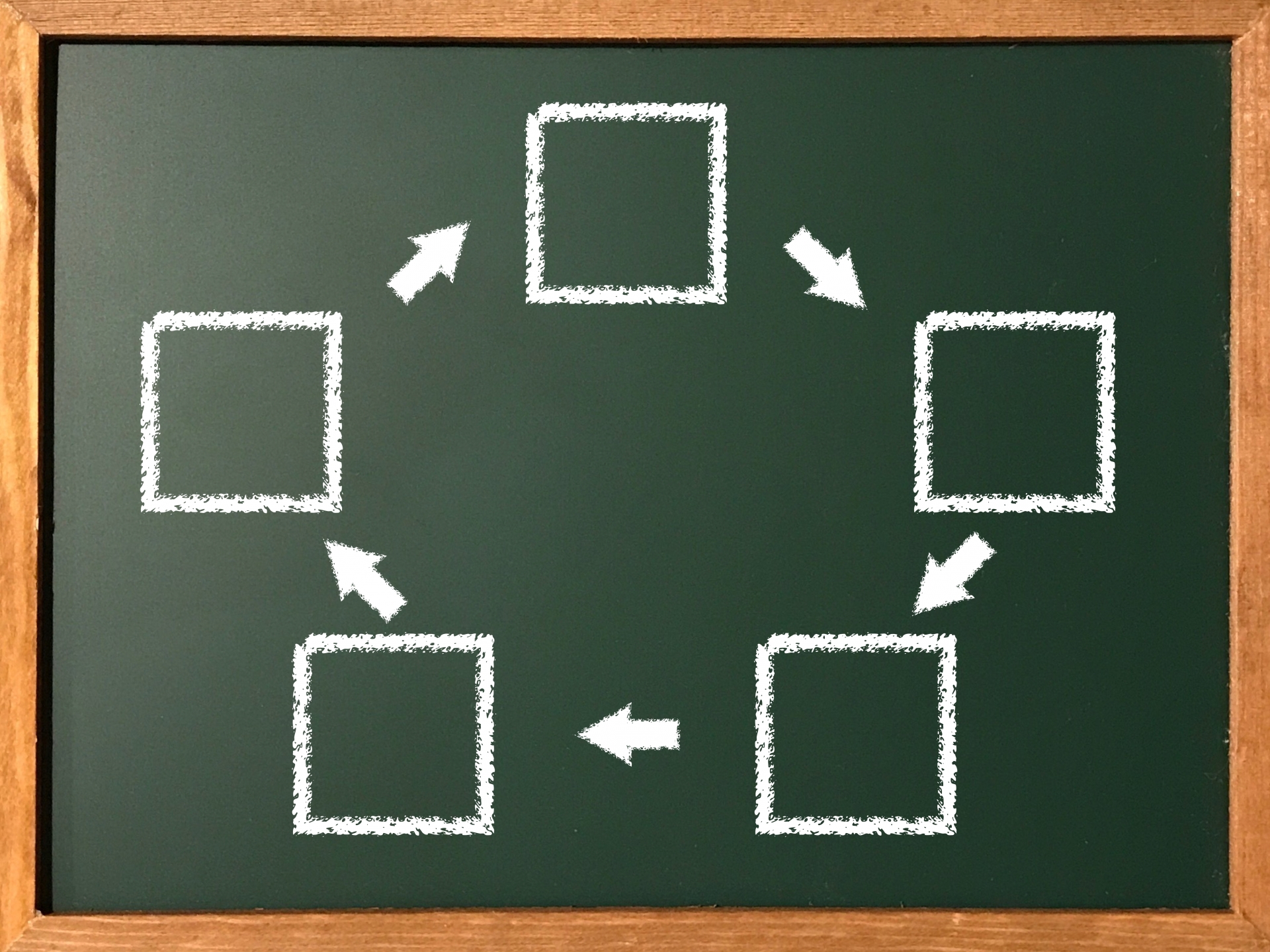


コメント